この記事は約3分で読めます!
「ジェネラリスト」を目指すべきか「スペシャリスト」を目指すべきか、ビジネスパーソンならば一度は聞いたことがあると思います。
今回は「ジェネラリスト」と「スペシャリスト」どちらを目指す方が「稼いだり」「成功したり」できるのでしょうか?
結論か言えば人生100年時代においては、「スペシャリスト」を目指すべきです。
では何故「スペシャリスト」を目指すべきなのでしょうか?
その理由を今回の投稿では書いていきます。
ジェネラリストとスペシャリストの違い
「ジェネラリスト」とは、営業・総務・マネジメント等どんな部署でも対応できるような柔軟性がある人材
「スペシャリスト」は、特定の分野に関する深い知識やスキル経験があって、高いパフォーマンスを発揮する人材
◎ジェネラリストは様々な知識を広範囲に持っており、転勤や転籍などの大企業の総合職に多く見られる職能です。
極めて、日本型の人材と言えます。例えば新卒で「総合職」「一般職」と言う募集要項がありますが、概して「総合職」の方が「一般職」よりも給与が多い場合がほとんどです。
これは「転勤」があったり、「営業」を3年やった後「人事部」に移動になったさらに2年後「マーケティング部」に移動となりさらに「役職」がついたといった具合です。
「出世」や「昇給」などその会社内での知識や技能は習得しやすいと言えます。
広い視点で考えると、「終身雇用」「年功序列」「新卒一括採用」の日本型雇用ではジェネラリストが生まれやすいと言えます。
◎一方スペシャリストは、業務範囲が狭く特定分野に特化して仕事をする人を指します。外資系の企業に多く見られます。
外資系の企業は「実力主義」です。つまり結果を出さないとクビです。
そこには、年齢・転職回数・男女など関係ありません。「成果」を出し続けないと生き残れない世界ですので、学び続けなければ生き残れない世界なのです。
変化に対応する力も持ち合わせないといけません。
今の日本では経済の「グローバル化」「デジタル化」によって、「ジェネラリスト」よりも「スペシャリスト」が重宝される時代になってきていると言えます。
例えば、IT化によってITを使いこなす人材は企業側でも重宝されるようになってきています。
またIT化や効率化を提案する「コンサルタント」も重宝されるでしょう。
さらには、今の日本では「大量生産・大量消費」の時代ではないため一人一人のニーズが違ってくるために、きめ細かな営業活動が必要です。
そうなったときに「大企業」で働いた「ジェネラリスト」よりもニーズに合わせた形の「スペシャリスト」が貴重な存在となるのです。
では「スペシャリスト」を目指すとどのようなメリットがあるのか具体的に書いていきます。
スペシャリストは転職・独立しやすい
スペシャリストの職種を具体的に挙げると、
・医者・会計士・弁護士・SE・プログラマー・コンサルタント・ケアワーカー・介護福祉士・証券アナリスト・為替ディーラー・管理栄養士・薬剤師・税理士
などでしょうか?他にもあると思います。
そしてこれらの職種は資格が必要なものばかりです。スペシャリストの場合、職場内で替えが効かない職種の場合が多いです。
替えが効かない分、転職市場や再雇用の場では即戦力として重宝される可能性が高いです。
その人材に貴重価値がある場合が多く、顧客が多いのも特徴です。
そのため、独立しても稼げる可能性があります。
一方でジェネラリストは、様々な部署を経験することで社内評価は高まっても社外で稼ぐ事が出来る力は身についていない場合も良くあります。
社内での評価=社会のニーズに必ず合うかというとそういった訳ではありません。
副業などを例にとっても、同じことが言えます。個人として勝負する場合に「部長」の肩書よりも「WEBコンサルタント」「プログラミングができる」
と言った方がニーズはあると思いませんか?
会社内だけで通用する力は、「終身雇用」制度が崩壊したりその企業が事業再編・縮小・倒産などによってなくなってしまう可能性があります。
会社外でも通用する力を身につける必要があります。
スペシャリストは問題解決力がつく
スペシャリストの職種は、問題があったときに解決を図ってくれる職種ばかりではないでしょうか?
例えば、会社内でパソコンがフリーズしたとかサーバーやクラウドが落ちたとかした場合解決してくれるのはエンジニアやプログラミング設計者です。
揉め事があって当事者同士で解決できない場合は、警察や弁護士に頼みますよね。
業務効率化や業務拡大のアドバイスや具体的な解決を自社でできない場合外部のコンサルタントが解決への道筋を教えてくれる場合もあります。
病気に掛かったら、病院に行き医者に診てもらう、薬剤師に薬をもらう病気の症状が重ければ重いほどこういった職種の人に頼るしかないです。
いくらAIや人工知能が発達しても、自身が難病にかかって医者や看護師・薬剤師全てがロボットだったら人生終わったと思いませんか?
優秀な医師や数々の難手術を達成した人に頼みたいと思うのが普通ではないでしょうか?
何が言いたいかと言うと、スペシャリストの仕事が人々の悩みや困っている事を解決する職種だという事です。
日々の生活や仕事においては、「想定していない」事が日常茶飯事で起きます。
そこで、誰かがやってくれるだろうや自分には関係がないと思わずに率先して想定外の出来事を解決することで専門的な事を知り問題を解決する第一歩となります。
それがスペシャリストへの第一歩と考えます。
スペシャリストは変化に対応しやすい
スペシャリストは第一線で活躍している場合が多いため、マーケットのニーズの変化に敏感だと言えます。
例えば、ブログよりも今後は動画の時代が間違いなく訪れるだろうその根拠として、動画を中心としたサービスが多くを占めているからであるという事で
ブログ⇒Youtubeをメインに動画市場で有益なコンテンツを提供しようとかです。
またYoutubeとブログをミックスした形も試してみようなど「スペシャリスト」だからこそ市場の変化に敏感だと言えます。
別の例を挙げると、会計士や税理士がAIにとって代わる可能性があって危機感を抱いてる職種ならば、AIにできて人にできることは何かを考えます。
つまり差別化を図れという事ですが、会計や税理の基礎概念があれば後はそこにプラスαのサービスを
提供する事やアフターフォローなど人にしかできない事に注力を注ぐ事が可能となります。
スペシャリストは個人の価値がつく
スペシャリストになればなるほど、その人にしかできない貴重な価値を提供できます。
前述したようにスペシャリストは問題を解決したり、営業の場面でもその人しか売れないとかその人に頼みたいと思わせる営業が出来れば
それは同じ営業マンでも差別化が図れているのだと思います。個人として価値を提供出来れば、取引先や顧客から再度お願いがされます。
一方でお客様は役職がついた人に頼みたいと思うのではなく個人に頼みたいと思うわけで「ジェネラリスト」はそういった場面では不利と言えるのではないでしょうか?
スペシャリストは個人の時代を反映している
会社の名前を頼らずに、自分の名前とスキルだけでどれだけ通用するか考えたことはあるでしょうか?
私自身も恥ずかしながら、まだ収入面で会社に依存せざるを得ない状況です。こうしてブログでの広告収入やアフェリエイト収入を目指して頑張っていますが
実を結んでいません。
しかしながら、今後の人生において収入が会社員だけというのは非常にリスクが高いです。また年齢と共に「人的資本」が少なくなっていく事も事実です。
仕事の技能が全く同じの20代と50代の人材ならば、採用する側が間違いなく20代を選ぶでしょう。20代の方が「人的資本」が豊富でかつ、将来利益をもたらす
可能性を秘めているからです。
背景にあるのは、「終身雇用の崩壊」「年功型賃金」の崩壊が挙げられるのですが、日本の大企業を中心に未だに「年功型賃金」が色濃く残っている部分もあります。
そこには「挑戦」よりも「安定」を望む風土が残っているのですが、そのポジションや部署が合併や売り上げ縮小または機械化・効率化・AI化等
によりなくなると「個人ブランド」が社会に向けて確立されていなければ厳しいと言えます。転職はおろか非正規雇用となる可能性もあります。
最悪、待っているのは加齢にジリ貧もしくは貧困となり中高年の引きこもりの一員となって「8050問題」と向き合わなければいけない可能性もあるのです。
「個人ブランド」を確立するにはスペシャリストを目指すべきなのです。
スペシャリストは簡単になれるものではありません。結果が全てだからです。結果がダメならば実力主義では「さようなら」と言って見向きもされません。
「一生懸命頑張っています」でも結果はまだ出ていませんでは評価されません。「一生懸命頑張ってこれだけ成果が出ました」でないと評価されない世界です。
このブログ運営がいい例です。本投稿は134投稿目となるのですが、収益が上がらなければどれだけ書いても意味はありません。
人はリスクを取らずにリターンだけ得ようとしますが、リスクとリターンは表裏一体です。
そして思考停止で現状維持や安定を取ろうと言うこと事体が実は「リスク」であることに気づかねばなりません。
何故ならば危機が現実となったときにはもう遅いからです。
転職市場の話をすると、現在は「売り手市場」で企業が人材に来てくださいと言っている時代です。超高齢社会で少子化が進む日本では労働力が少なくなる一方です。
有効求人倍率はバブル期並みとなっています。
しかし、一方で非正規雇用者数は伸び続けています。これは企業が誰でもいいから来て下さい。と言っているわけではなく「欲しい人材」「いい人材」が不足している
と言っているに過ぎません。
これは個人で起業したり、フリーランスとして活躍したい場合においても全く同じことが言えます。
「稼げる個人」「全く稼げない個人」と2極化する可能性があるのです。
私自身も危機感をもって、「選ばれる人材」「稼げる個人」を目指していきたいと思います。
✔ スペシャリストは様々な問題を解決に導くため、需要やニーズの変化に対応しやすい
✔ 転職・独立・副業の分野においてはスペシャリストを目指すべき
✔ 会社を一歩出たら「役職」ではなく「個人ブランド」で勝負しなくてはいけない。それまでに培ってきたスキル・人脈など個人の名前で本当に勝負できるか今一度考えよう。

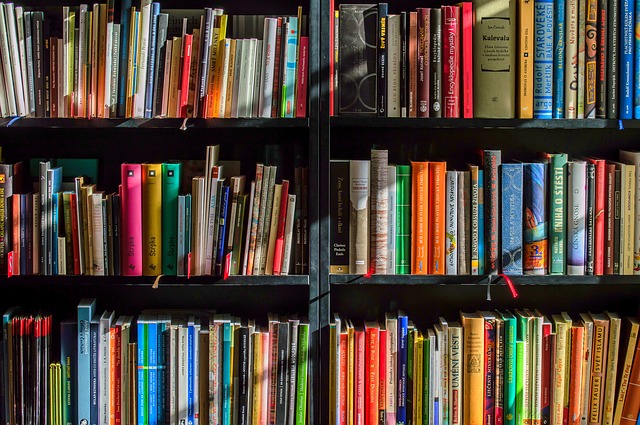

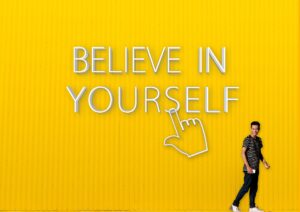






コメント